1月14日、丹生川町旗鉾の伊太祁曾神社で、伝統の管粥神事(くだがいしんじ)が執り行われました。この神事は、農作物の出来や天候など当年の運勢を占う行事として630年以上前(1391年頃)から伝えられ、市の無形文化財に指定されています。占いが的中するなど地域内外から注目されており、地元の皆さんを始め報道関係者も詰めかけます。
今回は、この伝統行事を通じて地域の歴史文化を学ぼうと、まち協主催の参拝学習ツアーを企画し、11名の皆さんが参加しました。地域の歴史に詳しい田中彰さんから、神社や神事の歴史について解説いただき、同神社の若手氏子で構成する若連中(大頭 前田康介氏)が中心となって執り行う神事を見守りました。
お湯を沸かした大きな釜に、米と大豆、小豆の穀類と占い項目を示すサワラの木札を付けた管(麻の茎)を入れ炊き上げること約一時間。釜上げされた管を一旦神前に供え、その後1つひとつ小刀で切り開いて粥の入り具合を確認し、筆で管粥帳に記録。今年は101項目の吉凶を占いました。
月例では10月が最良で、景気は乗鞍関係が良好。台風や地震は終盤に注意が必要。農作物ではトマトが最良で、かぼちゃやごぼう、紅かぶ、トウモロコシ、ねぎが良好。プロ野球のペナントレースでは、セ・リーグは横並びだが終盤中日が良好か。パ・リーグはオリックスと西武が優勢。今年9月に開催の世界陸上では、100mと400m、20キロ競歩の活躍が期待されるとのことです。
炊きあがったお粥は、1年の無病息災を願って参拝者に振舞われました。皆にとって、良い1年になりますように。


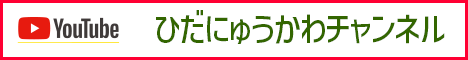



コメント